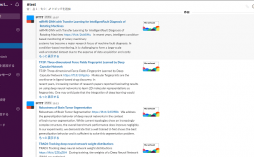HPC
HPC M6g 触ってみた (2) -OpenFOAM ベンチマーク結果-
はじめに
前回の記事でAWS EC2 M6gインスタンスに使われているGraviton2についての簡単な紹介と、HPLベンチマークの結果を掲載しました。今回はOpenFOAMについてのベンチマーク結果をご紹介します。実のところA1インスタンスの登場時にも同様の検証を行っていましたが、当時はこのブログもなかったので、私が参加した勉強会などのLT等で紹介するにとどまりました。
ベンチマーク内容
これも前回触れましたが、OpenFOAM-v1912をUbuntu20.04LTS標準のgcc-9.3.0, OpenMPI-4.0.3でビルドしました。ベンチマークデータは弊社も賛助会員のオープンC...